 |
| 時刻表の索引地図では、鹿児島県の中心駅は2つ。=「JR時刻表」より |
突然ですが問題。日本でいちばん南に鉄道が走っている県は? 沖縄県には今は走ってないので、九州は鹿児島県が正解。最も南の駅は西大口(指宿枕崎線)という日本一有名な無人駅。なんと言ったって、稚内駅に「西大口まで…」という看板があるくらいだ。
ではもう一問。その鹿児島県の中心駅は?
「鹿児島駅!」
「いや、西鹿児島駅!」
どちらが正解でしょうか、時刻表を見てみましょう――と、JR時刻表の「索引地図」を見てみる。「都道府県庁所在地駅、代表駅」には◎印が付いているのである。北海道なら「札幌駅」、福岡県なら「博多駅」。東京都は「東京駅」と「新宿駅」と2つあるけど、東京駅は新幹線が通る巨大駅だし、都庁が近いのは新宿駅だから止むを得ない。では鹿児島県は…。「鹿児島駅」に◎です。よって正解は鹿児島駅。
「ちょっと待った〜! 西鹿児島駅も◎だぞ!」
なぬっ!? 地図を見るとビックリ、鹿児島本線で鹿児島駅の一つ隣、西鹿児島駅にも◎印があるぞ。これはどうしたことか…。
◆2つの「中心駅」の謎
鹿児島には、2つの中心駅が隣接して存在するという恐るべき事実が発覚した。そこで識者に伺うと、
「『中心駅』の定義が曖昧だから、こうなるんですよ。きちんとしてれば、どっちか1つになる」
彼が言うには、『中心駅』というのは次のような定義が考えられるという。
都道府県庁の最寄駅→これが大多数
(例)札幌、新宿、千葉、福島、奈良、山口、鹿児島
県庁の最寄駅ではないが、特急や急行が発着する駅
(例)東京、大阪、西鹿児島
交通の要衝駅
(例)博多
駅そばがうまい
(例)京都
|
|
あまり関係のなさそうな定義もあるが、ともかく行政や文化など地域の中心的な位置にあるのが中心駅だという結論である(そのままだ!)
あくまでも都道府県庁所在地の最寄駅が「中心駅」とすべき、と彼は主張する。ただ、東京の場合は、かつて東京駅の近くに都庁があったが新宿に移転したという背景から例外的に2つ認めているのだという。ちなみに旧都庁跡地は現在、「東京国際フォーラム」になっている。
「じゃあ、鹿児島はどう説明するの?」とたずねた。
「大阪だって、本来の最寄駅理論で行けば大阪城北詰駅(JR東西線)が府庁最寄駅なわけだ。でも、こんな駅、大阪の人しか知らんでしょ」
「地理的にこだわらず、実質的な中心を考えるってこと?」
「それでも漠然としちゃう。大阪だって天王寺や難波があるからね。そこで、2つ目の特急列車の発着がポイント」
「新幹線は新大阪だぞ。大阪発着の特急も、そんなにないぜ」
「でも新大阪か大阪だろう。新大阪は、大阪駅の代替的な位置付けだ。ホラ、営業規則では、新大阪発着の姫路以遠は大阪発着とみなしてるでしょ」
この議論は朝まで続いたので以降を省略するが、結論としては
『鹿児島と西鹿児島は位置すら違うが同じ駅!』
という無茶苦茶なものとなった。んなわけんーだろ、駅間は営業キロで3.2kmも離れてるんだぞ、どう考えたって同じ駅ではない。
「おまえ、本当は理由、分からないんだろ?」
「あ、鍋がふいてるから、また今度ね」
なんちゅう逃げ方だ。
識者は当てにならん。とりあえず、分かっていることを羅列してみよう。
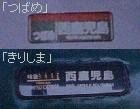
ETN |
鹿児島駅は鹿児島本線、日豊本線の終点である。西鹿児島駅は鹿児島本線の途中駅で、指宿枕崎線が分岐している。
鹿児島本線の「つばめ」、日豊本線「きりしま」は、どちらも西鹿児島発着。
でも、「きりしま」は鹿児島駅にも止まる。
寝台特急「なは」は西鹿児島発着。かつて「はやぶさ」「富士」も西鹿児島発着だった。
近い将来できる九州新幹線は、なんと西鹿児島駅に発着する。
鹿児島県庁、鹿児島市役所は鹿児島駅が最寄駅。
旅人の心のオアシス、鹿児島中央郵便局は西鹿児島駅の前にある。
でも、これだけでは謎は解けない。これだけ大きな問題を抱えて放ったらかしにするなんざ、男が廃るってもんよ。
――我々は、現地突撃取材を行うことを決意した。
◆「名」の鹿児島、「体」の西鹿児島
突撃取材に相応しい、春の心地よい風の吹く日であった。
取材費を捻出するだけで大変だったため、当然「宿無し・飯無し・観光無し」の三無しで決行した。
博多駅から夜行特急「ドリームにちりん」に乗り込み、車中爆睡、翌朝早くに宮崎駅に降り立った。寝ぼけていたのか、駅構内にあるJR直営のコンビニ「生活列車」で牛乳石鹸を買っている。これは食べられないので、ぐっと堪えて特急「きりしま」に乗り込み、一路、国分駅へ。
国分駅からはJRバスに乗って、桜島へ行く、と。
「どこが観光無しなんだ! いきなり桜島に行ってるじゃないか」
「チッチッチ、甘い甘い。きちんと取材のことは考えてるのよ」
せっかく来たので溶岩展望台に行ってみる(バリバリ観光です)。いっちょうらんの洋服が火山灰まみれになる。あれは洗濯してもなかなか落ちない。鹿児島市民のみなさんは大変だ。
そして、桜島からフェリーで鹿児島市内のフェリーターミナルに到着。
そのフェリーターミナルから歩いてすぐのところに、問題のJR鹿児島駅があるんです。どーだ!
「フェリーターミナルから歩いてったら、たまたま鹿児島駅だったんじゃないか?」
えー、とにかく、鹿児島駅に着いた。
驚愕、とは、まさにこのことを言うのだろう。
2つの本線の終着駅、つまり全国でも青森駅とここぐらいにしかない位置付けの駅なのである。そう、見えますか?
駅前に鹿児島市電の駅やバス停があるけど、そちらのほうが駅よりも大きくて賑やかなような気がする。
ここまで来たのだ、と勇気を振り絞って駅構内に入ってみる。ちょうどいい列車があれば、西鹿児島まで電車で移動しようと思っていた。階段をあがって2階部に改札や駅事務室がある。
上に行くと、窓口がひとつ、改札ひとつ、券売機2つ。壁際にはパンフの入った箱。改札のうえに、パタパタ式(電光式じゃないやつ)の発着案内板。
「・・・・・・。」
私、そして同行記者ともども無言になった。次の鹿児島行き電車は1時間半後!
これまでの疑問が、すべて吹き飛んだ。
もうひとつの中心駅、西鹿児島駅へは、電車を待つ気もないので、市電で移動することにした。バスと競争しているようで、抜いたり抜かされたりするのは面白い。どちらも信号は止まらなくてはいけないから速度は同じだが、専用道(路面電車)を走る市電の方が悠々している感じ。
ほどなくして、西鹿児島駅に着いた。通称「西駅」。
こちらは、新幹線が来ることを見越して改築されている。隣駅と比べたら、誰が見てもこちらが中心駅、である。
「西駅」前の中央郵便局に入って、涼みながら考えた。今回の謎解きの旅の答えを。
「誰が見ても、西鹿児島のほうが中心だと思うよな。規模も綺麗さも、人の数も違う」
「でも、あくまでも『西』鹿児島駅なんだね。『鹿児島駅』があってこその『西』鹿児島、というわけだ」
「鹿児島の市街地は、いま路面電車乗ってわかったが、『鹿児島』と『西鹿児島』の間にあるんだ。どちらの駅の前、というわけでもない」
「つまり、中心駅をどちらか一方にすることに、あまり意味はないということだ。『鹿児島』は、県庁が近いということもあるが、路線上の結節点だし、なにゆえ『鹿児島』と名乗っている。一方、『西鹿児島』は機能的に見て、実質的に鹿児島県の中心駅だが、あくまでも『西』なんだね」
「名と体をとると、どうしても両方を中心駅とせざるを得ないんだな」
少なくとも郵便局のロビーでやる議論ではないようであるが、おかげで結論に達した。
『べつに2つ中心駅があったって、いいんじゃないの?』
ホント、現地取材までやって出た結論なんざ、こんなもんだったりして・・・。
|