|
ここでは主に近鉄難波駅について書くつもりなのだけど、その前にまず難波について「難波をめぐる冒険」と題して概観し、その後、近鉄駅について詳しく記すことにしよう。
●「難波をめぐる冒険」
どこかで次のような文を読んだことがずっと頭に残っていた。
「…東京駅は別格として、新宿と大阪(梅田)がA級ターミナル駅、池袋と難波がB級ターミナル駅である。」
僕は今までに、この5つの駅のうち「難波」だけ行ったことがなかった。
まず、東京駅は、暇なときに用もなくよく行く。新宿駅はそれ程なじみがあるわけではないけれど、京王線を利用するため行ったことがある。大阪(梅田)駅は旅行途中に乗り換えのため何度か利用した。池袋駅は映画を見に昔行ったことがあるし、他にも豊島園に遊びに行くときに西武線に乗り換えたことがある。
行ったことがないので当たり前だが、難波のことはよくわからない。これでは難波に失礼だ(?)──ということで先日、難波を訪れてみた。目的は言うまでもなく「B級ターミナル駅・難波」を体感することである。
行ってみて、思った。
「いったいこれでターミナルといえるのか?」
確かに、難波には「難波」(または、「なんば」)という名のつくJR、南海、近鉄、大阪市営地下鉄(千日前線、御堂筋線、四つ橋線)の駅がある。しかし、それぞれがとても離れているのだ。
僕はJR、南海、市営地下鉄それぞれの難波駅を見て回ろうと思っていたのだが、これが思いのほか時間がかかった。これほど1つ1つが離れていてはもはやターミナルとは呼べないのではないか? ターミナルとは乗り換えが便利であることも条件の一つであるはずだ。
もう少し詳しく順を追って説明しよう。細かい説明が嫌いな人、飛ばしてください。
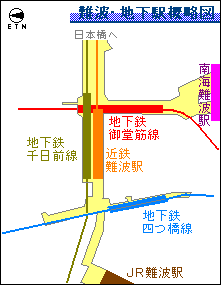 |

ETN |
JRで難波入りした。JR難波駅はまだ開業して比較的新しいせいか、綺麗な雰囲気があって、雰囲気は悪くなかった。開通したてのあの都営大江戸線の駅みたいな感じだ。
改札を出て5分くらい歩くと、市営地下鉄の駅の前を通った。四つ橋線だったと思う。そのあと2分くらい歩くと近鉄と、たぶん千日前線の入り口。ところで、僕は近鉄で難波を離れようと思っていたので、先に南海駅訪問を済ませることとした。よって今度は南海なんば駅を探す。
看板に従って歩くことさらに5分以上、途中御堂筋線の改札口を横目に、やっと南海駅の改札口に到着した(余談だが、南海駅改札口のエスカレーターには面白い広告がある。「関西空港にはラピートがはるかに速い」というもの。わかってしまう人にはにんまり笑える広告だ)。
さてさて、南海なんば駅の活気を確かめた後、気持ちを新たに近鉄駅を目指す。来た道をたどってなんとか近鉄駅と千日前線駅の入り口へ。
朝9時頃だったからよかったが、もしお店が開いてお客が通路を歩いていたらどうなったか? あるいはもう少し早かった場合、つまり通勤ラッシュ中ならば、もっと時間がかかっただろう。
もちろん、僕のような行程(つまり3つも4つも駅をまわること)は、普通はあり得ない。本当は、それぞれ2つの駅間の距離を問題にすべきである。でも、JRと南海の駅が遠いのは確かだ(ただし地下通路を利用したとき。地上の場合は…知らない)。
でも、この両駅を乗り換えする人はあまりいないだろうな。せいぜい『ラピートα』に是が非でも乗りたいという人くらいだ。
結論。難波を一つのターミナル駅として捉えることは無理である。今にして思う、これこそB級の意味ではないか?
●行き当たりばったり
話の重点は近鉄難波駅に移る。実質、「百名駅・近鉄難波駅編」はここから始まる。長い前置きだったが諒とされたい。
近鉄駅の自動券売機の前で僕は考えていた。これからどうするのか?
正直言って、僕の旅行はいつも行き当たりばったりである。例外もあるが、一人のときはまず間違いなく行き当たりばったりが貫かれる。今回はやはり例外ではなく、しかも行程中、特に分岐点だとは思われないところで考えるはめになった。
大事な場所ではない、というわけではない。むしろ後の乗り換えを考える上では悪くない位置だ。JR難波駅に着いたときは、「難波をめぐる冒険」に心を奪われていて、余裕がなかったし、これ以降先だと、例えば鶴橋まで行っては選択肢が狭まりかねない。だから、繰り返すが、ここは悪くない位置なのである。
考えても埒があかなかったので、運賃表を見てみることにした。これは僕の旅行テクニックで、運賃表を見るとよいアイデアが生まれることがある。
「うーむ…。さすがに難波から阿倍野橋までの切符は買えないか…」
などと、くだらぬことを考えていると、頭がすっきりしてきた。これからどうすべきか見えてくるような気がした。そうしてついにある結論に至った。
「実際電車に乗れば、自然と決まるだろう」
………。
一応、鶴橋までは近鉄に乗ることとし、200円区間の切符を買った。で、切符を自動改札機に入れる。バタン、という味気ない音を聞きながら、僕は改札を抜けた。
近鉄難波駅のホームの構造について紹介しておこう。
難波駅には乗車ホームと降車専用ホームの2種類がある。降車専用は1つであり、ここで奈良・名古屋方面からの乗客を降ろす。
降車ホームで人を降ろした列車は、そのまま乗客を新たに乗せることはせずに、いったん「奥」に引っ込む。その後、また今度は乗車ホーム(「1のりば」、「2のりば」)に入線する。
名古屋行きの特急列車が「1のりば」であり、奈良線方面の快速急行・急行・準急・普通が「2のりば」である。伊勢志摩方面の特急電車は難波始発ではない。隣の隣にある、近鉄の本拠地・上本町始発である。
ところで、このホームの構造、かなり大変だと思いませんか? 何が大変かというと…、ヒント、近鉄難波駅の発車時刻。
下に平日の13時台の難波駅の発車時刻表を掲げよう。
| 特 急 | 00、30 (ともに名古屋行き。ただし00分発はノンストップ) |
| 快速急行 | 02、22、42 (全て奈良行き) |
| 急 行 | 12、32、52 (快速急行に同じ) |
| 準 急 | 17、37 (西大寺行き)、57(奈良行き) |
| 普 通 | 14、27、34、54(西大寺行き) 07、47(東生駒行き) |
|
(数字は分。2000年3月15日改正の「近鉄難波駅時刻表」より抜粋)
もう少しわかりやすくするために、これを並べ替えてみよう。
00,02,07,12,14,17,22,27,30,32,34,37,42,47,52,54,57
ホームの数のわりにすごい数だと思いませんか? なんと1時間に17本! これを仮に降車ホームの場合を考えると、終着駅という忙しい駅で、1つのホームだけで約3分ごとの列車を処理しなくてはならないのである。終着駅なので特急列車は乗客を降ろすのに時間がかかるだろうし、忘れ物の点検などあるかもしれない。酔っ払いもいるかもしれない。
夕方のラッシュ時である19時台だと、なんと21本! これは列車がよほどダイヤ通りに運行していないと大変な数字である。
実際見てみるとよくわかる。僕は15分ほど難波駅のホームにいたが、その短い時間に何台もの電車がやってきては「奥」に消えた。
降車ホームばかり書いたが、乗車ホームの回転も速い。乗車ホームは「1のりば」と「2のりば」があると書いたが、「1のりば」は特急専用なので快速急行以下は「2のりば」だけでさばかなくてはならない。降車ホームに劣らずとも勝らずである。
ちなみに乗客の方も結構忙しい。すぐに来てすぐに行くから、それでまた、快速急行、急行、準急、普通、と種類が豊富だからどれに乗ってよいか、慣れていないと間違えてしまう可能性がある。
もう一言。先ほどから降車専用ホームと乗車ホームがあると書き、降車ホームで乗客を降ろした列車はいったん「奥」に引っ込むと書いたが、この「奥」はいったい何者か? 聞くところによると、以前から近鉄難波と阪神西九条をつなぐ計画があるらしい。この「奥」はその名残ではないかというのである(この計画が未だに進行中か、あるいはとん挫したのかどうかは僕は知らない。興味がある方は調べてみてください)。
それにしても「奥」は大変そうだ。「奥」にどれくらい線路があるかはわからないが、暗闇の中で、列車たちはせわしなく線路を変えているのだろう。
さっき書いたが、僕は15分ちょっとくらい、ホームでぼお〜っとしていた。
列車が来てはいなくなりまた現れる、その繰り返し。たまに回送列車なんかも来て、ホームで列車の行き来を見ているだけでも飽きなかった。今回の旅路の中で間違いなく最高の瞬間(?)でした。
(2002年7月追記)
|